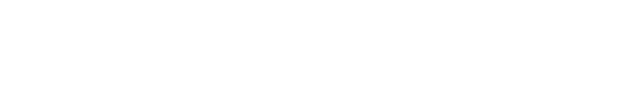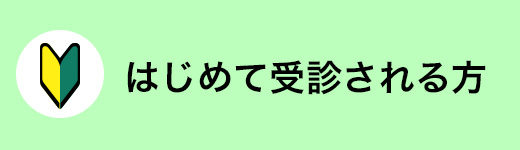健診結果が届いた方
検査結果表の見方
2025年度より、日本人間ドック・予防医療学会に準拠し各検査の基準値および判定区分の見直しを行いました。2024年度までとは判定区分に変更がございますので、ご確認をお願いいたします。
| 区分 | 2024年度まで | 2025年度から |
| A | 異常を認めません | 異常を認めません |
| B | 軽度異常、日常生活には支障ありません | 軽度異常、日常生活には支障ありません |
| C | 経過観察 |
要再検査(3・6・12か月) / 生活改善 C3 3か月後の再検査 C6 6か月後の再検査 C12 12か月後の再検査 |
| D | 要再検査 | 要精密検査/要治療 |
| E | 要精密検査 | 治療中 |
| F | 要治療または治療継続 | ー |
身体計測
▸BMI「体重/身長(m)²」で計算されます。疾病が少ないのは”22”とされています。
基準値:18.5~24.9
▸標準体重「身長(m)²×22」で計算した値を、標準体重としています。
▸脂肪率 体重にたいして脂肪がどれだけあるかを示したもので「%」で表されます。
眼科系検査
▸眼圧検査 高いと緑内障や高眼圧症が疑われます。低い場合は、網膜剥離や外傷などが疑われます。
基準値:8~21
▸眼底検査 白内障、緑内障、網膜色素変性症などの目の病気だけではなく、動脈硬化や糖尿病などによる血管の変化を見ることができます。
よくみられる眼科所見
乳頭陥凹 眼球は視神経で脳とつながっています。眼底検査で眼の中をのぞくと、眼底のほぼ中心にほんのりと赤い視神経の出口が見えます。これを視神経乳頭と呼びます。乳頭陥凹は、緑内障のときに大きくなりますので、乳頭陥凹を指摘されたときは眼科専門医を受診して、視野・眼圧などの精密検査を受けましょう。
黄斑変性症 網膜の一部、黄斑部が光により老化し排出作用が衰えて老廃物が蓄積し、だんだん見えなくなったり、まぶしく感じるなどの症状や視野の中心部がぼやけて見えたり歪んだりします。眼科専門医を受診して、精密検査を受けましょう。
循環器系検査
心電図や血圧検査の他、胸部X線検査で得られる心臓、大動脈などの異常をみます。心臓超音波検査(オプション検査)では、心臓の大きさや心臓壁の厚さや運動、弁の状態(弁狭窄や逆流)心臓内での異常の有無を観察、心臓の機能を評価します。
よくみられる心電図所見
ST上昇 心電図のST部分が通常より上昇しています。心筋炎、心筋梗塞などの時に現れます。健康な若年者でもみられます。
ST低下 心電図のST部分が通常より下がった状態です。心臓の筋肉での血液の流れが悪い場合や、心臓の筋肉が厚くなった心筋症などで起こります。
陰性T 心電図波形のうちで通常は山型をしているT派が谷のようにへこんだ状態です。多くは心臓の筋肉に負荷がかかった状態や障害により起きます。
右脚ブロック 伝導路のなかで心臓の右側部分で電流が途絶え、左側から電流を流してもらっている状態です。加齢とともに起こりやすくなる病態です。
左脚ブロック 心電図の中で心臓の左部分で電流が途絶え、右側から電流を流してもらっている状態です。ほとんどの場合、心臓疾患が原因で起こりますので、原因を調べる必要があります。
不完全右脚ブロック 左右心室への刺激伝導の時期に、ずれがある時に多くみられます。
左室肥大 心臓弁膜症や高血圧などにより、心臓の左側にある左室の容積が大きくなったり、筋肉が肥大していることでみられる現象です。
心室性期外収縮 電気の発生源が通常ではない心室部位から、通常のリズムよりも早く発生した状態をいいます。多くの心疾患のとき、または健康な人でも、興奮・喫煙・過労の時などに見られます。出現頻度や原因、症状によっては治療が必要となることがあります。
上心室性期外収縮 心臓の上部から余分な電気が発生して心臓を刺激する場合をいいます。緊張・興奮・ストレスなどで起こることもあります。時に、発作性頻拍や心房細動になることがあります。
低電位 心電図の波の高さが低くなる所見です。体内の水分貯留や肺に含まれる空気の増加などで起こります。
心電図所見については、症状・心音・胸部X線検査などを総合して検査を必要とする場合があります。
呼吸器系検査
▸肺機能検査(スパイロメトリー) 肺の動きを検査します
▸%肺活量 性別・年齢・身長から算出された肺の容量に対して、肺活量が何%であるかを調べます。
▸1秒率 最大に息を吸い込んでから一気に吐き出すとき、最初の1秒間に何%の息を吐き出せるか(気管支での空気の流れやすさ)を調べます。
▸胸部X線検査や喀痰細胞診検査 主として肺がんのスクリーニングをします。また、肺感染症とその既往、心疾患などもスクリーニングします。
血球系検査
▸赤血球(RBC) 肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る役目を担っています。少なすぎると貧血、多すぎると多血症や脱水が疑われます。
基準値:男性 438~539万/μl 女性 376~489万/μl
▸血色素(ヘモグロビンHb) 血色素とは赤血球に含まれるヘムたんぱく質で酸素の運搬役を果たします。
基準値:男性 13.1~16.3g/dl 女性 12.1~14.5g/dl
▸ヘマトクリット(Ht) 血液全体に占める赤血球の割合です。
基準値:男性 40.4~51.9% 女性 34.3~45.2%
▸白血球(WBC) 白血球は細菌などから体を守る働きをしています。
基準値:3.1~8.4 10³/μl
▸血小板(PLT) 血小板は出血したとき、その部分に粘着して出血を止める役割を果たしています。
基準値:14.5~32.9 10⁴/μl
脂質系検査
▸総コレステロール(TC) 血液中に含まれている脂質です。
基準値:140.0~199.0mg/dl
▸HDLコレステロール 善玉コレステロールと呼ばれるものです。血液中の悪玉コレステロールを回収します。
基準値:40mg/dl 以上
▸LDLコレステロール 悪玉コレステロールと呼ばれるものです。
基準値:60~119mg/dl
▸中性脂肪(トリグリセライド) 体内で最も多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。
基準値:30~149mg/dl
高脂血症の大部分は栄養過剰、アルコール過飲などが原因です。糖分、動物性脂肪の摂りすぎに注意し、野菜・果物等の繊維質の多い食事を摂りましょう。また適度な運動を心がけましょう。
糖代謝
▸血糖値 血液中のブドウ糖で、エネルギー源として全身に利用されます。
基準値:99mg/dl 以下
▸HbA1c 過去1~2か月の血糖の平均的な状態を知ることができるので、糖尿病のコントロール状況がわかります。
基準値:5.5%以下
肝臓・胆嚢・膵臓系検査
▸AST(GOT)・ALP(GTP)・γ‐GTP 肝臓の細胞内に存在する酵素です。肝障害により細胞が壊れると血液中に出てきて高値となります。γ‐GTPはアルコールや薬物に酵素誘導作用があり、脂肪肝、アルコール性や薬物性の肝障害などで、高値になることがあります。LDH・ALP・CHE・ZTT・ビリルビンなども肝機能の他、胆道系機能を調べることができ、これらを総合的にみて判断します。
基準値:AST(GOT) 30U/L以下 ALP 37.0~118.0U/L γ‐GTP 50U/L以下
▸HBs抗原 B型肝炎ウイルスによる感染を調べます。抗原が陽性(+)の場合は感染していることを示しますが、肝炎を発症するとは限りません。
▸HBs抗体 抗体が陽性(+)の場合は過去に感染があり、免疫ができていることを示します。また、HBVワクチン接種後の効果をみることもできます。
▸HCV抗体 C型肝炎ウイルス(HCV)による感染を調べます。陽性(+)の場合は過去から現在の感染を疑います。
▸アミラーゼ アミラーゼは食物として接種したデンプンを消化する酵素で、主に膵臓と唾液腺で作られています。
基準値:39.0~125.0U/L
腎・尿路系検査
▸尿検査 尿中の各種細胞、蛋白、糖などを調べます。蛋白、潜血は腎臓病や尿路系の疾患で陽性になります。
▸尿素窒素・血清クレアチニン 体内でエネルギーとして使われたタンパク質の老廃物です。通常は尿中に排出されますが、腎機能が低下すると血液中に残ってしまい高値になります。
基準値:尿素窒素 8.0~20.0mg/dl 基準値:血清クレアチニン 男性 1.00mg/dl以下 女性 0.07mg/dl以下
▸尿酸 尿酸は体内のサビ(アルコールや火を通した油などの酸化物質)に対し、サビ止めの役割を担う物質のひとつで、高尿酸血症はサビが体内に増えたことを意味します。
基準値:2.1~7.0mg/dl
炎症系
▸RF リウマチ因子を持つ物質を調べるものです。陽性ならリウマチが疑われます。
基準値:15.0U/ml以下
▸ASO A群溶連菌の抗体の強さを見るために行われるもので、上昇すれば溶連菌の感染があったと考えられます。
基準値:240.0U/ml以下
▸CRP 細菌、ウイルスに感染するなどで炎症が発生した時に血液中に増加する急性反応物質の1つが CRPです。多くの疾患で上昇し、疾患によって上昇の度合いが違います。
基準値:0.30mg/dl以下
消化器系検査
胃部X線・内視鏡検査は、胃・十二指腸の疾患の有無を調べます。X線検査は粘膜面の色調が分からないので、炎症などを調べるには内視鏡検査が適しています。
▸ヘリコバクターピロリ菌検査 ピロリ菌は胃に住む細菌です。萎縮性胃炎や胃・十二指腸潰瘍を認める方は、除菌治療が必要です。ピロリ菌の有無を確認する検査(定量)である尿素呼気検査をお受けください。
▸ペプシノーゲン 血液中のペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比を調べると陽性であれば胃粘膜に萎縮があると考えられ萎縮性胃炎、胃がピロリ菌に感染し、胃・十二指腸潰瘍などが疑われます。この検査のみでは判定できませんので、陽性の場合、胃部内視鏡検査による精密検査をお受けください。
よくみられる消化器系所見
胃ポリープ 粘膜からイボのように隆起しているものをポリープと呼びます。ほとんど経過観察でよいものが多いです。
萎縮性胃炎 胃の粘膜が萎縮して薄くなってくるために、粘膜の下にある血管が透けて見えた状態になっています。
表層性胃炎 胃粘膜表面に赤い充血をみる炎症です。
胃・十二指腸潰瘍 粘膜の傷の深さによって、びらんと胃潰瘍に分けられます。びらんは粘膜の比較的浅い部分(粘膜下筋板)までの傷をいい粘膜下よりも深くまで傷ができた場合を潰瘍と呼びます。ピロリ菌感染、一部の内服薬、日常のストレス、タバコやお酒の飲み過ぎなどが原因になります。ピロリ菌が原因の場合は治療が必要です。
びらん 胃が荒れている状態です。
腹部超音波検査
肝臓・膵臓・腎臓に腫瘍があるかや、胆のうには胆石などがあるかを調べます。
よくみられる腹部超音波所見
肝血管腫 血管が増殖して出来た腫瘍で良性です。ただし、大きい場合や初めて見つかった場合は、確定診断目的で精密検査をする必要があります。
肝嚢胞 肝臓内部にできた独立した袋状組織です。中には液体または半固形体が入っています。通常は経過観察で治療の必要はありません。
脂肪肝 脂肪滴を伴う肝細胞が30%以上認められる場合を脂肪肝といい、以前は、アルコールによるものが多かったのですが、糖尿病や肥満などの生活習慣病で発症することが多くなっています。
胆のう結石 胆のう内にカルシウムやコレステロールなどの成分の石が形成されています。
胆のうポリープ 胆のう内にできたポリープの事です。自覚症状はありません。急に大きくなるものや、形が不整なもの、大きさが10mm以上のものは精査・治療が必要です。
膵管拡張 膵臓から十二指腸へ通じている膵管が拡張しています。結石や腫瘤が原因となることもありますので精査が必要です。
膵嚢胞 膵臓内にできた独立した袋状の組織です。袋には液体が含まれています。所見がある場合、念のため精密検査を行います。
腎石灰化 腎臓にできたカルシウムの沈着のことです。
腎嚢胞 腎臓内にできた袋状の組織で、基本的には心配のないものですが、壁や内部の状態に不審な点があれば、精密検査で確認します。
超音波検査は反射波を集めて行う検査です。リアルタイムで多方向から観察ができる、軟部組織の描出能が優れているなどの長所がありますが、骨や空気の存在に弱い、視野が狭いなどの欠点もあり、判断が困難な場合もありますので、他の検査と併せて診る必要があります。
乳房検査
視触診、マンモグラフィ(X線)、超音波検査で乳腺疾患をみます。
よくみられる乳房検査所見
乳がん 乳房にある乳腺に発生する悪性腫瘍です。遺伝子的な要因など、様々な原因が考えられますが、欧米型の生活やストレスが関係しているともいわれます。乳がんの症状は様々で、しこり・血性乳頭分泌・乳頭の陥没・皮膚のくぼみ・脇の下のしこりなどです。
乳腺症 一般的な良性の乳腺の変化を乳腺症といいます。乳腺過形成・年齢や女性ホルモンによる変化を総称していいます。症状は、乳房のしこりとともに緊満感・痛み・乳頭分泌などを認めます。乳腺症を疑われた場合、正常あるいは良性のものであることがほとんどですが、中にはきわめて良性か悪性か診断の難しいものがありますので、気になるしこりなどがありましたらご相談ください。
繊維線種 繊維線種は充実性のしこりで、がんではなく良性の腫瘍です。触れると弾力があり、繊維組織と腺組織からできています。繊維線種は、若い女性に多く、10代でも見られることがあります。原因は不明です。
石灰化 乳房の石灰化は分泌物によるもの、がん細胞が壊死した物質に石灰沈着が起きたもの、動脈硬化によるものなどがあります。その形状や分布状態で良性か悪性か判断できる場合もあります。区別がつきにくい場合もあり、区別が難しい石灰化、悪性が疑われる石灰化については、細胞検査・組織検査などが必要になります。乳房疾患に関しましては、セルフチェックと定期的(年1~2回)に検査を受けることが大切です。気になるしこりなどの症状がある場合は、お早めに専門医を受診してください。
婦人科検査
婦人科検査でよくみられる所見
子宮筋腫 子宮にできる良性の腫瘍で、30~50代の女性の4~5人に1人はもっているとみられます。貧血になるほど月経血の量が多い、また下腹痛や腰痛がひどい場合は早めに受診しましょう。大きさや症状、年齢などを考慮して、手術や薬物療法などの積極的治療の選択をおすすめする場合や、定期的に診察を受け、様子を見ていく場合がありますので、主治医と相談しましょう。
子宮内膜症 子宮内膜という組織が子宮の内側以外の卵巣や子宮の周辺部に出来て増殖する病気で、若い女性に増えています。月経痛が激しく月経以外の時でもお腹や腰に激しい痛みが現れます。月経痛がだんだんひどくなってきた場合は要注意。なるべく早く診察を受けましょう。
卵巣腫瘍(良性) 卵巣腫瘍の80%以上は良性だといわれており漿液性嚢胞腺腫・粘液性嚢胞腺腫・奇形腫などがあります。良性の卵巣腫瘍では、内部が主に水検査などで初めて発見されることが少なくありません。卵巣腫瘍は漿液性、粘液性の嚢胞腺腫をまとめたものをいい、良性腫瘍に属しますが、中には悪性に変化するものもありますのでチェックが必要です。小さく良性と判断された場合には経過観察しますが、直径5cm以上のものは手術療法を考慮します。
卵巣腫瘍(悪性) 卵巣腫瘍の中で、悪性の代表が卵巣がんです。卵巣がんでは、液体以外に細胞のかたまりが多いことが特徴であるといわれてます。10代から高齢者まで幅広い年齢でみられ、最近増加傾向にあります。自覚症状がないため初期には分かりにくいことが多い病気ですが、内診や経膣超音波検査で診断されることが少なくありません。子宮がんの健診時に、卵巣も一緒に検査してもらいましょう。卵巣嚢腫や子宮内膜症のある方は必ず、定期診察をうけてください。
子宮頸がん 子宮の入口付近(頸部)にできるがんで、若い女性にも比較的多く見られます。主に性交渉で感染するHPV(ヒトパピローマウイルス)といわれるウイルスが原因のひとつで、性交渉の経験のある女性なら誰でも感染する可能性はあり、子宮頸がん患者の90%はHPVに感染しているとの報告もあります。感染したら必ずがんになるわけではありませんが、初期は全く無症状で、進行するにしたがって異常なおりもの、不正性器出血、性交時出血、下腹部痛などの症状がみられてきます。早期発見のためにも1~2年に一度の検診を受けましょう。
子宮体がん 子宮の内膜(体部)にできるがんで、子宮内膜がんともよばれ、近年増加傾向にあります。好発年齢は50~60歳で、閉経後の女性に多い病気ですが、30~40歳代の女性にもみられます。30歳以降の月経不規則、エストロゲン服用歴、出産経験のない女性、肥満や高血圧、糖尿病がある女性は要注意です。主な自覚症状は不正性器出血やおりものの異変です。異常を感じたらすぐに診察をうけましょう。
| 子宮頸部細胞診検査判定(ベセスダ分類) | 推定される病理診断 | 運用 | 判定 | ||
| 扁平上皮系 | NILM | 陰性 | 異常なし |
異常なし (定期検診継続) |
A |
| ASC-US | 意義不明な異型扁平上皮細胞 | 軽度扁平上皮内病変疑い |
要精密検査 ※当施設では状況に応じて、他の医療機関をご紹介させていただいております |
E | |
| ASC-H | HSILを除外できない異型扁平上皮細胞 | 高度扁平上皮内病変疑い | |||
| LSIL | 軽度扁平上皮内病変 | HPV感染・軽度異形成 | |||
| HSIL | 高度扁平上皮内病変 | 中等度異形成・高度異形成上皮内がん | |||
| SCC | 扁平上皮がん | 扁平上皮がん | |||
| 腺系 | AGC | 異型腺細胞 | 腺異型または腺がん疑い | ||
| AIS | 上皮内腺がん | 上皮内腺がん | |||
| Adenoca-rcinoma | 腺がん | 腺がん | |||
| Other marig | その他の悪性腫瘍 | その他の悪性腫瘍 | |||
| 子宮体部細胞診検査判定 | 運用 | 判定 |
| 陰性 | 正常範囲内(定期検診継続) | A |
| 疑陽性 |
要精密検査 ※当施設では状況に応じて、他の医療機関をご紹介させていただいております |
E |
| 陽性 |
終夜睡眠ポリグラフィー検査
結果の見方はこちら
動脈硬化検査
結果の見方はこちら